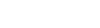How often should you clean your kimono? Don't overdo it! The correct way to care for your kimono to keep it beautiful for a long time

Kimono is a traditional Japanese costume, and because of its beauty and formality, it is often worn in formal situations, but many people are confused about how to care for it. In particular, one of the questions that many kimono users have is, "Should I have it dry-cleaned immediately after wearing it?"
Here we will explain the correct frequency for cleaning kimonos and the best care methods depending on the situation. In order to keep your kimono beautiful for a long time, be sure to acquire the necessary knowledge and daily care habits.
The frequency of kimono cleaning should be determined based on how often you wear it and the occasion.
The frequency of cleaning kimonos cannot be simply determined as "once every ◯ number of times." It is important to make a comprehensive judgment based on multiple factors, such as the type of kimono, the occasion when it is worn, the season, and the storage conditions after use.
Here, we will explain in detail the differences between everyday wear and formal wear, why dry cleaning every time can be counterproductive, how to care for your kimono before the off-season, and the recommended frequency of dry cleaning for different types of kimono.
Why do you need to clean your everyday clothes and formal clothes at different frequencies?
The frequency of use and how easily it gets dirty differs greatly between everyday kimonos and formal kimonos such as furisode and houmongi. For example, everyday kimonos made of cotton or wool are prone to sweat and sebum, so they require frequent care depending on how often they are worn.
On the other hand, formal silk kimonos are worn infrequently, so if they are only slightly soiled, it may be sufficient to simply dry them in the shade and refold them without having to clean them.
Difference in points
|
kinds |
Ease of getting dirty |
Frequency of wearing |
Cleaning Guideline |
|
Cotton and wool |
expensive |
frequently |
Needed once every few times |
|
Silk formal kimono |
low |
Several times a year |
About once or twice a year |
Rather than "always wash after wearing," it is important to make decisions based on the material and purpose.
Is cleaning every time counterproductive? What is the recommended frequency to clean clothes gently?
The idea of "drying immediately after wearing it once" can actually damage the fabric. Silk is particularly delicate, and frequent washing can easily damage the fibers and have a negative effect on the texture and color. Ideally, dry cleaning should be done at the appropriate time, such as when there are noticeable stains or sweat stains, or before storing for a long period of time.
Aim for the following frequency:
・If worn all day: Once a year to once a season
・Short-term wear: Dry in the shade and brush, then check at the end of the season.
・If there is a lot of sweat or food stains: consult a specialist store immediately after wearing
As such, the key to making your kimono last longer is to flexibly decide the frequency of cleaning depending on how you wear it.
Cleaning timing required before storage and off-season
When considering how to store kimonos, the most important thing is to keep them clean from the time they were stored. Even if the dirt is not visible to the naked eye, it can cause stains and mold during long-term storage. Therefore, it is recommended to clean the kimono at the change of seasons or when you know that you will not be wearing it for a long time.
Things to do before the off-season:
・Check the condition of the kimono (dirt on collar and cuffs, sweat stains)
・Request full wash or stain removal if necessary
・After cleaning, it is a good idea to use an oxygen-free pack or insect-proofing treatment.
The important thing is to "reset any dirt before storing it for a long period of time."
Differences in frequency of cleaning for furisode, houmongi, and mourning clothes
There are many different types of kimono, each with different purposes, decorations, and frequency of use. Therefore, the frequency of cleaning varies from one type to another. It will be easier to decide if you classify them as follows.
|
Types of Kimono |
Frequency of use |
Features |
Recommended cleaning frequency |
|
Long-sleeved kimono |
Limited occasions such as coming-of-age ceremonies and weddings |
Many decorations and gorgeous |
Immediately after use or about once a year |
|
visiting clothes |
Worn for tea ceremonies and other ceremonies |
Mainly silk and elegant design |
If it's not dirty, about once a year. |
|
Mourning clothes |
Suddenly worn at funerals, etc. |
Black dye makes dirt less noticeable |
Check and judge each time you wear it. |
Because these kimonos are expensive and delicate, it is advisable to consider having them cleaned after consulting with a specialist store.
There are different ways to deal with stains on kimonos depending on the type.
In order to maintain the beauty of your kimono, it is essential to know the correct way to deal with different types of stains. Even if it looks clean at first glance, invisible dirt such as sweat and sebum can accumulate in the fabric and cause future stains and discoloration.
In addition, first aid taken to prevent problems such as spilled food or mud splashes can affect the lifespan of a kimono.
Here we will explain the specific countermeasures and precautions for each type of dirt.
Beware of invisible dirt such as sweat, sebum, and foundation
When wearing a kimono, sweat, sebum, and cosmetics ingredients adhere to the fabric without you even realizing it. The areas around the neck and cuffs are particularly prone to getting dirty as they come into contact with the skin. These stains oxidize over time and appear as yellowish or brown stains, so it is important to take measures before they become noticeable.
Measures you can take in your daily life
After wearing, be sure to dry in the shade to remove moisture.
・Lightly brush the collar and cuffs
・Occasionally ask for sweat removal or spot washing at a specialty store
Because sweat and sebum are colorless and transparent, they are easily left untreated, but early care can prevent problems from occurring.
Correct first aid and procedures for food spills, mud, and drink stains
The most common problems that can occur when you are out and about with your kimono are oil stains from food, mud splashes, and water stains from drinks. If left unattended, these will become permanent and become difficult to deal with. For this reason, it is important to know first aid methods that can be used while you are out.
Basic First Aid Procedures
|
Types of stains |
First aid methods |
|
Oil stains |
Gently press with tissue and do not rub forcefully. |
|
Mud splash |
Allow to dry and then brush gently. Do not touch when wet. |
|
Beverages (tea, coffee, etc.) |
With a damp cloth, absorb the liquid by tapping from the outside towards the center. |
However, first aid is only temporary, so ultimately it is best to have it dealt with at a specialist store. After first aid is done, be sure to take it to a dry cleaner right away.
What happens if you leave dirt on your kimono? Examples of problems with kimono fabric
Leaving unnoticeable stains can cause serious damage to the fabric of a kimono. Sweat and sebum in particular easily penetrate the fibers, and over time they oxidize, causing stains, mold, and even deterioration of the fibers.
Actual common trouble cases
・Yellowing around the collar is now impossible to remove
・Mold has developed on the lining of a black kimono, and cannot be removed even after washing it.
・Mud splashes on the hem of a formal kimono were left unattended, causing discoloration and hardening, leading to the fabric cracking.
All of these problems occur as a result of "thinking that the kimono is not dirty and leaving it as it is." The key to keeping your kimono beautiful and long-lasting is to be wary of invisible stains and to carry out regular inspections and early treatment.
Understand the differences in cleaning methods and choose the best one
Kimono cleaning can be broadly described as a single method, which includes full washing, stain removal, and washing and stretching, and each method has a very different purpose and finish.
If you want to keep wearing a particularly precious kimono for a long time, it is important to understand the meaning of the cleaning menu and choose the appropriate treatment that suits the kimono's material and condition of dirt.
Here we will explain the most common cleaning methods and costs, precautions for each material, and how to identify a trustworthy specialty store.
Features and price range of full washing, stain removal, and cleaning
There are three main methods for cleaning kimonos. It is a good idea to understand the differences between them and the situations in which they are suitable.
|
Method name |
Features |
Suitable Applications |
Price range (approximate) |
|
Fully washed |
Dry clean the entire garment with a solvent |
Light dirt, overall refreshment |
¥8,000〜¥14,000 |
|
Stain removal |
Pinpoint removal of specific stains |
Food spills, sweat stains, makeup stains, etc. |
Varies depending on the degree of dirt (approximately ¥3,000 to ¥10,000) |
|
Washing |
The kimono is taken apart, washed, and re-sewn. |
If the stain is severe, it may be necessary to remake the item. |
¥20,000 and up (re-tailoring not included) |
For particularly expensive kimonos, partial treatment or washing and stretching may be more effective than full washing. Don't judge based on price alone, but choose based on the condition and use of the kimono.
How to choose cleaning methods that vary depending on material, color, pattern, and tailoring
Kimono are made of various materials such as silk, cotton, wool, and polyester, and each has its own appropriate cleaning method. In addition, the shade of the color and pattern, as well as decorations such as gold leaf and embroidery, are also important factors that affect whether or not the item can be cleaned.
Important points to note regarding materials and tailoring
・Silk: Very delicate, wash as little as possible. Be careful of moisture and friction.
Gold leaf and embroidery: May come off with regular dry cleaning. Professional treatment required.
- Lined: Sweat tends to accumulate in the lining, so consider removing sweat or washing the lining.
By understanding the characteristics of the fabric, you will be able to make the best decisions when choosing the best treatment. Before sending it to the dry cleaner, be sure to clearly explain the fabric and tailoring at the store to prevent any problems.
How to choose a reliable specialty store based on national qualifications and track record
To leave your kimono cleaning to someone else, it is essential to leave it to a professional with proven skills. Be careful, as general cleaning shops may lack the equipment and knowledge required for kimonos.
Tips for choosing a specialty store
・Holds a national qualification for kimono cleaning (cleaning technician)
・There are many examples of construction work, and before and after photos are available to the public
・The pricing structure is clear, and they will provide you with a plan that matches the material and tailoring you want.
・A full range of options are available, including storage services, water-repellent treatments, and oxygen-free packs
For example, when it comes to expensive kimonos such as furisode or houmongi, the risk of trouble can be greatly reduced by entrusting the task to a specialist company with a wealth of experience in handling luxury items.
Daily care habits to maintain the beauty of your kimono for a long time
In order to keep your kimono beautiful for a long time, it is essential to take good care of it after wearing it. Rather than sending it to expensive dry cleaners frequently, it is important to prevent damage and the accumulation of dirt through daily habits.
Here we will introduce practical maintenance methods, from basic care that can be easily done at home, to how to fold and store, how to use wrapping paper, and even storage methods that suit your age and lifestyle.
Basic care to prevent dirt and moisture by brushing and drying in the shade
After taking off your kimono, it is best not to fold it immediately, but to dry it in the shade to remove any moisture. Leaving sweat or moisture on the kimono can cause mold and yellowing. In addition, brushing off dust and pollen with a soft brush or towel can help prevent dirt from becoming fixed.
Basic care flow
1. Hang the kimono on a hanger and dry it in the shade in a well-ventilated room (2 to 3 hours).
2. Gently brush off dust and pollen with a kimono brush
3. Once dry, fold it correctly in tissue paper and store it.
By taking thorough measures against humidity, you can greatly reduce problems with your kimono.
Correct folding and storage methods can prevent clothes from losing their shape or becoming damaged by insects
Most of the loss of shape and insect damage to kimonos is caused by mistakes when storing them. Wool and pure silk kimonos are particularly susceptible to insect damage, so it is important to use insect repellents and air them out regularly.
Also, if you learn how to fold clothes correctly, you won't put undue stress on the fabric and it will look beautiful when worn.
Storage points
- Fold flat and do not apply too much pressure
・Use clean tissue and replace it once a year.
・Place insect repellent in an appropriate location without direct contact with the insect.
When storing it, choose a dark place with low humidity. If you are storing it in a closet, we recommend using a wooden slatted base or a desiccant.
How to use wrapping paper and the ideal frequency for airing
Tato paper is a type of paper used to protect kimonos, so it is important to choose special paper that is highly breathable and dust-proof. By wrapping kimonos in tato paper rather than storing them directly, you can protect them from the elements, moisture, and insects.
It is recommended that you air out your clothes once or twice a year, and it is most effective to do so during dry seasons with continuous sunny weather (such as October or February).
The basics of airing
- Hang it on a hanger in a well-ventilated room and dry it in the shade for 3 to 4 hours.
After airing, brush it before storing it again.
・It is also efficient to replace the tissue paper and insect repellent at the same time.
Airing out kimonos is something that we tend to forget, but it is an essential habit to keep your kimonos in good condition for a long time.
Kimono storage and management styles to review based on age
Depending on your life stage, you may need to reconsider how you manage your kimono. For example, the furisode kimono you wore when you were young tends to be worn less as you get older. It is important to optimize your storage space and method of keeping your kimono according to how often you use them and your lifestyle.
Age-specific advice
- For those in their 30s and 40s: Since formal kimonos and small patterns will be worn more frequently, regular seasonal inspections and maintenance is recommended.
・For those in their 50s and 60s and older: Focus on mourning clothes and black formal kimonos, and strengthen measures against humidity. Consider remaking or sorting out kimonos that you no longer need.
The key to maintaining a good relationship with your kimonos is to classify them into "kimonos you use," "kimonos that hold memories," and "kimonos you want to pass on," and then choose the best storage method for each.
Washing kimonos at home is the last resort! Know the risks and safety measures
Many people think, "I want to save money on cleaning fees" or "I wish I could wash it easily at home...", but kimonos are very delicate clothing and washing them yourself carries great risks. If you really want to care for your kimono at home, it is essential to do so carefully with the correct knowledge and procedures.
Here we will explain in detail the risks of washing clothes at home, provide a manual on how to do it safely, and also examples of mistakes and how to deal with them.
What are the wrong washing methods that can cause shrinkage, fading, and discoloration?
Kimono fabrics are made from a variety of materials, including silk, wool, and polyester, but silk in particular is vulnerable to moisture and friction, and will deteriorate quickly if washed incorrectly. The following washing methods should be avoided at all costs.
Laundry habits to avoid
- Machine wash (no machine wash)
・Wash and rinse with hot water
・Use of fabric softener or bleach
・Dry in direct sunlight
All of these can cause shrinkage, fading, shininess, discoloration, etc. In the worst case scenario, the kimono may be so damaged that it cannot be restored to its original state, so washing at home should be considered a "last resort."
Responding to your desire to wash! A safety manual for home laundry
However, there may be situations where you simply cannot take your item to a specialist store, and in those cases, you will need to wash it carefully and in a specific way that suits the material and condition of the item.
Home laundry safety steps (simplified)
1. Wash only "everyday kimonos such as cotton and linen"
2. Use water below 30°C and neutral detergent (not suitable for silk)
3. Wrap in a bath towel and gently press wash → rinse → lightly spin dry
4. Hang it on a hanger and dry it flat in the shade.
5. Once completely dry, iron the garment to remove any wrinkles (use a pressing cloth).
The above is a measure to be taken only in emergencies or for inexpensive kimonos. You should never do this to expensive pure silk kimonos.
Examples of failures caused by self-care and how to deal with them
There are endless problems caused by washing kimonos at home or self-maintenance. From the following examples of mistakes, it is important to learn about the delicate nature of kimonos and to take care of them safely.
Common mistakes and how to fix them
|
Details of failure |
cause |
Solution |
|
The dress shrank |
Washed with hot water |
Consult with a specialist store for washing and re-tailoring |
|
Colors are bleeding |
Lack of knowledge about colors |
Request a color correction service from a specialist store |
|
Shiny skin |
Strong ironing |
This may be possible with a steam iron and a pressing cloth. |
In some cases, once a kimono is damaged, it may not be possible to restore it to its original condition. The best way to prevent this is to "keep self-diagnosis and treatment to a minimum, and consult a specialist store immediately if you feel any discomfort."
Professionals answer common questions about kimono cleaning
When it comes to cleaning kimonos, many people, from beginners to intermediates, have worries and questions like, "What should I do?" By having the correct knowledge, you can reduce your anxiety and handle your precious kimonos with peace of mind.
Here, we will pick out some of the most frequently asked questions and provide easy-to-understand explanations from the perspective of a professional kimono cleaning company.
Should I send it to the dry cleaners even if I've only worn it once?
In conclusion, cleaning is not necessarily required after wearing it once. However, depending on the duration of wearing, temperature, amount of sweat, environment of the venue (outdoors or indoors), etc., it may be necessary to clean it earlier.
Decision points
・In summer or when wearing for long periods of time → Sweat removal is recommended
・Wear when eating or drinking or during pollen season → Lightly brush and dry in the shade
・Formal wear for ceremonial occasions, etc. → Always check after wearing
Since moisture and sweat are more likely to weaken fabric than dirt, it is more important to assess the condition and take appropriate measures rather than simply washing it immediately.
What should I do if I find stains or mold during storage?
It is not uncommon to find mildew or yellow stains when taking out a kimono that has been stored for a long time. This is caused by sweat and moisture before storage.
What to do when you discover it
Stains: Consult a specialist store as soon as possible and request stain removal.
・Mold: Do not wipe it off forcefully, but dry it in the shade and then request professional treatment (mold removal processing).
Mold in particular can damage fibers, so do not try to remove it yourself. Instead, have the item professionally cleaned and treated with anti-mold agents to prevent recurrence.
How to find a reliable specialty store? Tips for choosing the right store
Choosing a reliable dry cleaning shop is very important because you are entrusting your precious kimono to them. Don't just decide based on the price, but make sure to make a comprehensive judgment based on their skills, track record, and service system.
Tips for choosing a restaurant that won't disappoint
・A cleaning shop that specializes in kimonos
・Construction results are published (before and after photos)
・Nationally qualified cleaning technicians on staff
- The price list is clearly stated for each kimono.
・Optional features include water repellent, mold prevention, and oxygen-free packs
The key is to find a store that you can be glad to entrust with your needs by referring to actual word-of-mouth reviews and reputations.
What is the difference in how to treat expensive kimonos and everyday clothes?
Depending on the type of kimono, the way it should be handled, how often it should be cleaned, and how it should be stored will vary greatly. For example, furisode and tomesode are only worn on formal occasions and therefore require special care.
|
Classification of kimono |
Features |
Differences in handling |
|
Expensive kimono (furisode, tomesode, houmongi, etc.) |
Silk material, many decorations |
After use, have it inspected at a specialist store, thoroughly washed, and given a water-repellent treatment. |
|
Casual clothes (cotton/wool) |
Washable material and frequent use |
Seasonal inspections and home washing options available |
Especially for expensive kimonos, it is important to properly maintain them even if they have only been used once, and to thoroughly treat them before storage.
summary
By gaining a better understanding of how often and how to clean your kimono, you will be able to keep your precious kimono beautiful for longer.
Unlike Western clothing, kimonos do not need to be dry cleaned every time. It is necessary to make a decision based on the occasion of wearing, the type of kimono, and the characteristics of the fabric. Kimonos made of silk are particularly delicate, and daily care and proper storage have a greater impact on the lifespan of a kimono than frequent cleaning.
The most important point here is to have a sense of balance: neither too little nor too much cleaning frequency is good. In addition, the participants were able to acquire concrete knowledge and habits necessary to protect their kimonos, such as the ability to notice invisible dirt and moisture, first aid at home, and how to choose a reliable specialty store.
Middle-aged and older women who want to enjoy wearing kimonos, and those who are not familiar with traditional Japanese clothing, should first try practicing proper maintenance based on accurate information. Living with kimonos should become more fulfilling and secure.